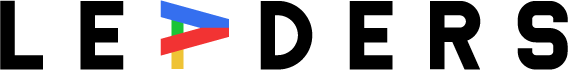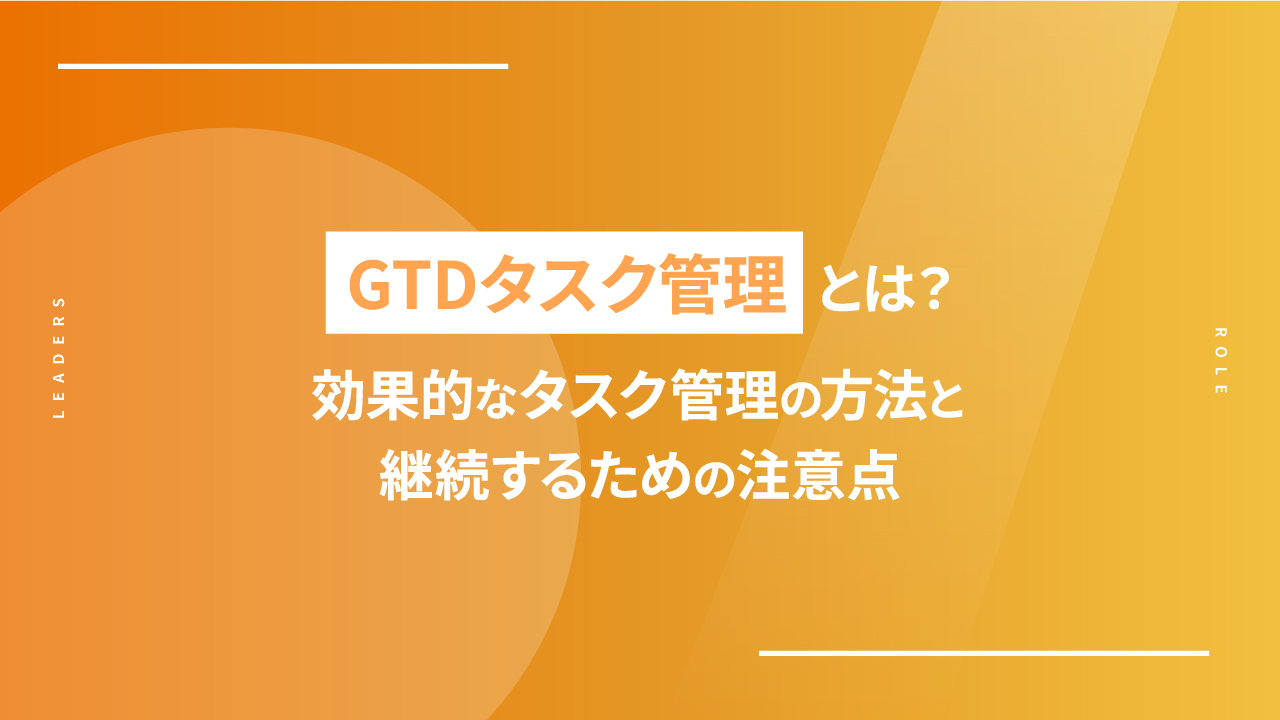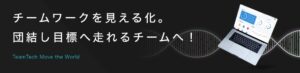今回は、効率的なタスク管理の手法「GTD(Getting Things Done)タスク管理法」をご紹介します。
時間管理と生産性の向上は、現代のビジネス環境において重要な要素です。また、日々のタスク管理も生産性向上には欠かせません。
GTDタスク管理は、仕事の優先順位を明確にし、意思決定のスピードを上げるのに役立つタスク管理の手法です。ただし、GTDタスク管理にはデメリットもあります。
この記事では、GTDタスク管理の具体的な手法や、よくある課題に対する対策まで深堀していきます。ぜひ、所属組織での生産性向上に向けた取り組みの参考にしてください。
【この記事の要約】
- GTDタスク管理とは、タスクの収集から優先順位付け、レビューや実行までをおこなう効率的なタスク管理の手法である
- GTDタスク管理は生産性向上などのメリットがある一方で、進捗管理に時間がかかるなどのデメリットもある
- GTDタスク管理を効率よくこなすには、汎用のMicrosoftofficeや、各種ITツールの導入がおすすめ
1. GTDタスク管理とは
GTD(Getting Things Done)は、生産性向上コンサルタント「デビッド・アレン氏」が提唱した、効率的なタスク管理の方法論です。GTⅮタスク管理は、頭のなかで考えているタスクを可視化し、優先順位をつけて実行する方法です。
【GTDとは?】
GTDはデビッド・アレン[1]が2002年に同名の書籍の中に提唱した個人ワークフローの管理手法である。主旨は脳内にある未解決の事を信頼できる外部システムに導入して管理し、脳に対する負担を減らし、目の前に行っている事に集中でき、目標を達成できるようにする方法である。
引用:早稲田大学 金群教授 指導 ワークフロー方式による個人学習支援システムの提案と評価より
GTDタスク管理を実践する流れを簡単に示すと、次のようになります。
- タスクの収集……やるべきタスクをすべて集めて可視化する
- タスクの明確化…… 収集したタスクを見極め、緊急度や必要なリソースなどを判断する
- タスクの優先順位付け……タスクに優先順位を付け、具体的なアクションを割り当てる
- タスクの選択と実行……優先順位に従ってタスクを実行する
- タスクのレビュー……定期的に進捗をレビューし、優先順位や未処理のタスクなどを見直す
一般的なタスク管理とGTDタスク管理との違い
GTDタスク管理の流れを見ると「通常のタスク管理と変わらないのでは?」と思うかもしれません。
GTDタスク管理と一般的なタスク管理とでは、次のような違いがあります。
| GTDタスク管理 | 一般的なタスク管理 | |
| 方法論 | タスク処理に関する具体的なステップが決められている | 個人の能力や管理方法に委ねられているケースが多い |
| ストレス | タスクを可視化し優先順位を決めて処理するため、ストレスが少ない | タスクが可視化されないためストレスを抱えることが多い |
| レビュー | 定期的にタスクを見直すため、優先順位が明確 | タスクのレビューをしないケースが多く、優先順位を見失いがち |
| タスクの量や質 | 複雑で多数のタスクを処理するのに最適 | 少ない量や簡単な質のタスク処理に向いている |
GTDタスク管理には、シンプルで効率よくタスクをこなすだけではなく、ストレスを減らし集中力を高められる効果があります。
GTDタスク管理ができるようになると、仕事をこなすうえでのストレスも軽減され、より重要な業務にリソースを割けるようになるため、結果として組織全体の生産性もアップします。
2. GTDタスク管理のメリットデメリット
GTDタスク管理法は、作業効率の向上などのメリットがある一方、準備やレビューに時間がかかる点など、いくつかのデメリットも存在します。
複雑で多数のタスクをこなすには、タスクの整理などに時間がかかるGTDタスク管理のほうが、結果的に高い生産性をあげられるケースも多いです。デメリットだけに注目するのではなく「最終的に生産性を上げる最適な方法はなにか?」をよく見極めて、自組織の状況に合ったタスク管理方法を選ぶようにしましょう。
GTDタスク管理のメリット「生産性向上とストレス軽減」
GTDタスク管理の、もっとも大きなメリットが「生産性向上とストレス軽減」です。
GTDタスク管理では、目の前のタスクを1ヵ所に書き出して可視化するため「優先順位が曖昧」「常に仕事に追われている感じがする」などのストレスからも解放されます。
また、可視化することでタスク検索に費やす時間も軽減され、生産性向上にも役立つでしょう。

GTDタスク管理のメリット「仕事の優先順位が明確になる」
GTDタスク管理のふたつ目のメリットは「仕事の優先順位が明確になること」です。
GTDタスク管理では、タスクを整理し、優先順位をつけて「優先度が高く、かつ緊急度が高い」順番で仕事をしていきます。そのため、重要な仕事に集中しやすくなり、緊急度が高いタスクを見逃すリスクも減らせます。
さらに、優先度が高い業務を洗い出すことで、経営幹部などに迅速な決済を仰ぐこともできるでしょう。優先順位が曖昧なままだと、期日が迫ってから決済を申請するなど、申請者と決済者両方が大きなストレスを抱えることになりかねません。場合によっては、正常な判断ができないケースが発生します。
簡単で優先順位が低い業務ばかり処理していては、組織全体の生産性も下がります。「やるべきことは頭のなかで整理できている」と思っても、意外に抜け漏れがあったり、整理できていなかったりするものです。
多少時間をかけてでも、タスク整理に重点を置くGTDタスク管理の手法は、大きなメリットを生むタスク管理方法といえます。
GTDタスク管理のデメリット「タスク設定と進捗管理に時間がかかる」

GTDタスク管理にはメリットが多い一方で、「タスク設定と進捗管理に時間がかかる」などのデメリットもあります。GTDタスク管理では、タスクを細分化し継続的に管理する必要があるため「管理作業にストレスを感じる」といった声も聞こえてきます。
GTDタスク管理のステップのなかでは、次のような管理作業が発生します。
- タスク収集と整理……GTDタスク管理では、既存のすべてのタスクを収集し、整理する必要がある。この時間を「無駄な時間」と感じるケースが多い
- ITツールの導入や管理……GTDタスク管理では、タスクの見える化をするためにMicrosoftofficeツールや、各種ITツールの導入が必要。有料ツールになると導入や管理にコストがかかるため、企業によっては負担となる
- 継続的なレビュー……GTDタスク管理では、タスクの継続的なレビューが必要。日々の忙しいスケジュールのなかで負担になるケースがある
ただ、上記のようなデメリットも、最終的に生産性が向上するのであれば「必要な投資」と考えることもできます。個人としても、タスクを優先順位付けすることで、より重要な業務に集中でき、結果としてスキル向上につながるケースも多いです。
GTDタスク管理を採用するかどうかは、短期的な目線で見るのではなく、組織全体のパフォーマンス向上や利益向上をよく考えて判断するといいでしょう。
GTDタスク管理のデメリット「自己管理能力が必要」
GTDタスク管理のふたつ目のデメリットとして、「自己管理能力が必要になる点」があげられます。
GTDを効果的に実践するには、継続的な自己管理が必要です。途中でタスク管理を投げ出してしまうと、この管理手法は機能しなくなります。
一般的なタスク処理では意識しないかもしれませんが、GTDタスク管理では次のような意識や管理能力が必要となります。
- 習慣化……タスク管理において新しい習慣を身につける必要があるため、過渡期には大きなストレスを抱える場合が多い
- 自己管理能力や整理能力……日々のタスクを定期的にレビューする必要があるため、高い自己管理能力が求められる
- 柔軟性や適応能力……変化する状況や優先順位に柔軟に対応する能力が求められる。一度決めたタスクの優先順位を変える必要もあるため、臨機応変な考え方が必要となる
ただ、上記の意識や管理能力は、ビジネスパーソンにおける「本来必要なスキル」ともいえます。GTDタスク管理で培われたスキルは、普段のプロジェクト進行やアイデア整理などの面でも活用できるかもしれません。
「GTDタスク管理は面倒で役に立たない」と短絡的に判断するのではなく、視座を一段上げて「GTDタスク管理がもたらすメリット」を、よく考えるといいでしょう。
3. GTDタスク管理の具体的な方法
さきほどご紹介したGTDタスク管理のステップ「収集」→「明確化」→「優先順位付け」→「実行」→「レビュー」の具体的な手法を見ていきましょう。
タスクを収集する
GTDタスク管理の最初のステップは「タスクの収集」です。具体的には、頭のなかで考えているタスクや、目の前の仕事をすべてノートやExcelなどに書き出し、可視化していきます。
タスク収集の段階では情報の整理が目的(優先順位の仕分けはしない)
タスクの収集段階では、タスクの優先順位を一切考慮に入れないことがポイントです。タスクの収集は、すべてのタスクを一箇所に集め、頭の中を整理するのが目的です。
タスクの収集にはアナログで書き出す方法もありますが、普段使いなれている「Outlookのタスク管理」などを利用して、思いつくままどんどん入力していくのがおすすめです。
タスクの収集では、情報の一元化も大きなポイントです。「ノートに書いたり、Excelに残したり」など、情報がバラバラだと管理できなくなるため、かならず情報は集約するように注意しましょう。
また、タスクの収集は一度やったら終わりではありません。日々やるべきタスクは増えたり減ったりします。あとで説明するレビューの段階で、定期的なタスク収集の見直しも必要になってきます。

タスクを明確化する
次のステップは「タスクの明確化」です。タスクの明確化とは「具体的に何をやるべきか?」を整理するステップのことを指します。
大きなタスクから小さなタスクへ分解し業務を明確化する
例えば「来年度までに新人を50人採用する」といった大きなタスクがある場合は、下記のような具体的なタスクに分解していきます。
- 人材募集や研修に関わるコストを予算化する
- 人材紹介会社などにオファーを出し採用条件を決める
- 具体的な採用広告を出稿する
- 面接日程を決め面談者との事前打ち合わせを実行する
- 具体的な入社スケジュールや研修スケジュールなど、他部署と打合せする
タスクの明確化のポイントは、
- 「何を」
- 「なぜ」
- 「どのように行うかおこなうか?」
を整理することです。タスクを明確化している途中で「1分以内に終わるタスク」が見つかったなら、その場で処理しておくと、後々の管理もやりやすくなります。
タスクに優先順位をつける
タスクが明確化されたら、つぎに優先順位や期限を決めていくようにしましょう。タスクの優先順位付けには、Microsoftofficeツールや有料の各種ITツールの利用が便利です。
優先順位別で期限を決める
さきほどの「来年度までに新人を50人採用する」タスクであれば、タスクの明確化で決めた仕事について、優先順位と期限を決めていきます。
※計画段階が2023年12月、実行が2024年4月~2025年3月の場合
- コストの予算化……2024年1月までに来年度の予算を確定する
- 人材紹介会社などへのオファー……予算に応じて2024年3月までにオファーを出す
- 採用広告の出稿……2024年4月~8月まで広告出稿する
- 面接日程に関する打合せ……広告出稿や応募状況に応じて面接日程を組む
- 入社後のスケジュール策定……2025年4月入社後のスケジュールを確定させる
タスクの重要度や緊急度を整理し優先順位をつけることで、限られた時間やリソースを、もっとも重要なタスクに割り当てられるようになります。このように整理していけば、大きな仕事を抱えるストレスからも解放されます。
タスクの実行
優先順位が決まったら、いよいよタスクを実行していきます。ここまでで優先順位や期限を決めているため、実行すべきタスクに集中して取り組むようにしましょう。
タスク実行に必要な環境やリソースを確保する
タスクの実行においても、むやみに取り組むのではなく、次の要素を整理しながらタスクをこなしていくのがポイントです。
- タスクを処理するための場所や環境を準備する
- いつまでにタスクを終わらせるべきか再確認する
- タスク処理に必要な時間を確保する
- タスク処理に必要なリソースを確保する
準備をせずに無計画にタスクに取り組んでしまうと、途中で仕事を投げ出してしまうかもしれません。特にタスク処理に必要な場所や環境の準備を怠ると、通常よりも多くの時間を費やすことになります。
タスクの実行は、優先順位を考えながら、計画性をもって取り組むようにしましょう。
タスクの更新(レビュー)
最後のステップは、タスクの更新(レビュー)です。タスクの更新は、さきほどの実行と合わせて取り組むべきステップですので、実行→更新→実行と、繰り返されることになります。
市場や職場環境の変化に応じて柔軟に対応する
GTDタスク管理は、一度タスクを決めたら終わりではありません。市場の環境の変化や、組織のニーズなど環境の変化に応じて優先順位を変えるなど、柔軟に対応していく必要があります。レビューした結果、処理する必要がないタスクも出てくるでしょう。
ちなみに、理想的なレビューのタイミングは、1日に1回です。朝、業務をはじめる前にタスクを見直し、一日の業務終了後に再度レビューするのが効率的です。もし、頻繁なタスクレビューが負担に感じるなら、1週間に1度程度でも問題ありません。
大事なことは「レビューを忘れないこと」です。予定表やスマホのアラーム設定をしておくなど、定期的なレビューを忘れない仕組みを作っておくといいでしょう。
4. GTDタスク管理でよくある課題と解決策
GTDタスク管理法を実行していくにあたっては、「タスク管理が続かない」「アナログ管理から脱却できない」など、いくつかの課題が出てきます。
代表的なよくある課題と解決策についても詳しくご紹介しますので、参考にしてください。
タスク管理が続かない

GTDタスク管理でよくある課題のひとつに、「タスク管理が続かず、つい惰性で仕事をしてしまう」というものがあります。細かくタスクを管理することに疲れてしまい、目の前のタスクや上司から言われた仕事を優先し、場合によっては優先順位が高いタスクを見落としてしまう場合があるかもしれません。
タスク管理が続かない最大の原因は「モチベーション低下」です。GTDタスク管理は、細かな管理が必要となるため、モチベーションが下がると「なぜ面倒な管理をしないといけないのか?」と、つい投げやりになってしまいます。
タスク管理でモチベーションを維持していくには、つぎのような方法がおすすめです。
- 達成しやすいタスクから取り組む……優先順位が比較的高く、達成しやすいタスクから取り組むと、達成感が得られモチベーション維持に役立つ
- 進捗を可視化する……ExcelやITツールなどを使い、終わったタスクを色付けするなど可視化する。タスク処理の進捗が可視化できるため、仕事を進めるたびにモチベーションが上がる
- ルーチン化する……GTDタスク管理そのものを毎日のルーチン業務として当たり前化してしまう
- 上司や同僚への報告……タスク処理の進捗を上司や同僚と共有する。まわりと共有すればアドバイスや協力が得られるケースも多く、モチベーションが保たれる
タスク管理の継続は「気合と根性」だけでは続きません。「モチベーションを下げない仕組み」も構築できるよう管理していくことが大切です。
チーム内でタスク割り振りに偏りが出る
チーム内でタスクの割り振りに偏りが出る点も、GTDタスク管理の課題のひとつです。
GTDタスク管理では優先順位の高いタスクを期限を決めておこなうため、どうしても優秀なスタッフにタスクが集中しがちです。ある程度の偏りは仕方がないかもしれませんが、チーム内で均等にタスクを割り振るには、次のような仕組みを作っておくのがおすすめです。
- 基準を決めてタスクを割り振る……タスクをいくつかのパターンに分ける。タスクのパターンごとで誰に割り振るかを事前に決め、チームメンバー全員の前で公開する。割り振りの理由や基準を公開すれば、メンバーからの不平不満も少なくなる
- 定期的なミーティングの実施……定期的なミーティングを通じて、チーム内のタスク進捗を共有する。ミーティングでは、進捗度合いやスキルをレビューし、必要に応じてタスクの再割り振りをおこなう
- 透明性のあるタスク管理ツールの使用……タスク管理ツールを使用して、タスクの割り振りと進捗をチームメンバー全員が共有できるようにする。これにより、透明性が高まりチーム全体での調整が容易になる
チーム内でのタスク割り振りに偏りが出る問題は、組織内のコミュニケーション不足がおもな原因です。「誰に何を割り振るのか?」「なぜ割り振るのか?」を明確にし、説明を怠らないようにすれば納得感も得られるでしょう。
アナログ管理から脱却できない

タスク管理では「アナログ管理からの脱却」が大きな障壁となる場合があります。
「ノートに書き出す」などのアナログ管理に固守したり、人によっては「頭のなかで管理できているから可視化する必要がない」と言ったりするケースもあるでしょう。特に長年アナログ方法でタスク管理をしてきた人々にとって、デジタルツールへの移行は大きな抵抗感を感じるかもしれません。
急激なシステム変更などは、組織内の軋轢(あつれき)を生じさせることにつながるため、次つぎのように柔軟に対応していくといいでしょう。
- 徐々にデジタル化へ移行する……「まずはタスクの収集だけをExcelに記録する」など、一部のステップのみ徐々にITツールへ移行する。
- アナログ感覚で使えるITツールを選ぶ……作業スタイルやスキルに応じ、使いやすさや柔軟性を重視したデジタルツールを選ぶ(操作性が簡単なものが理想)
- トレーニングとサポート……デジタルツールの使用に慣れるために、専門のサポート部署やサポート要員を決めておく(ツール提供のベンダーなどに長期間のサポートを依頼する方法もおすすめ)
GTDタスク管理におけるデジタルツールの使用は、あくまでも手段であり「タスク管理の目的」ではありません。
無理にアナログから脱却するのではなく、アナログとデジタルを上手に融合させながら、自組織にあった管理手法を選ぶようにしましょう。
進捗管理が難しい
GTDタスク管理は、ときに複雑な管理が伴うため「進捗管理が難しい」「管理するのが煩わしい」などといった問題が生じます。ときにはタスク管理に多大な時間と労力を要してしまい、タスク管理に過度なストレスを抱えてしまうケースがあるかもしれません。
進捗管理が難しいと感じたら、次のような対策を講じるといいでしょう。
- 進捗を過度に評価しない……少しくらいの進捗遅れがある前提で管理する。過密なスケジュールは組まない
- 柔軟性を持つ……「状況の変化に応じてタスク管理は柔軟に対応する」と最初から決めておく
- 管理に必要なツールを導入する……タスク進捗を自動的に可視化してくれるなど、自組織に合ったツールを導入する
GTDタスク管理を厳格に運用しすぎると長続きしません。ある程度は「進捗が遅れるもの」「優先順位は日々変わるもの」と、俯瞰的にとらえて管理するとストレスも軽減されます。
タスク管理に追われてワークライフバランスが保てない
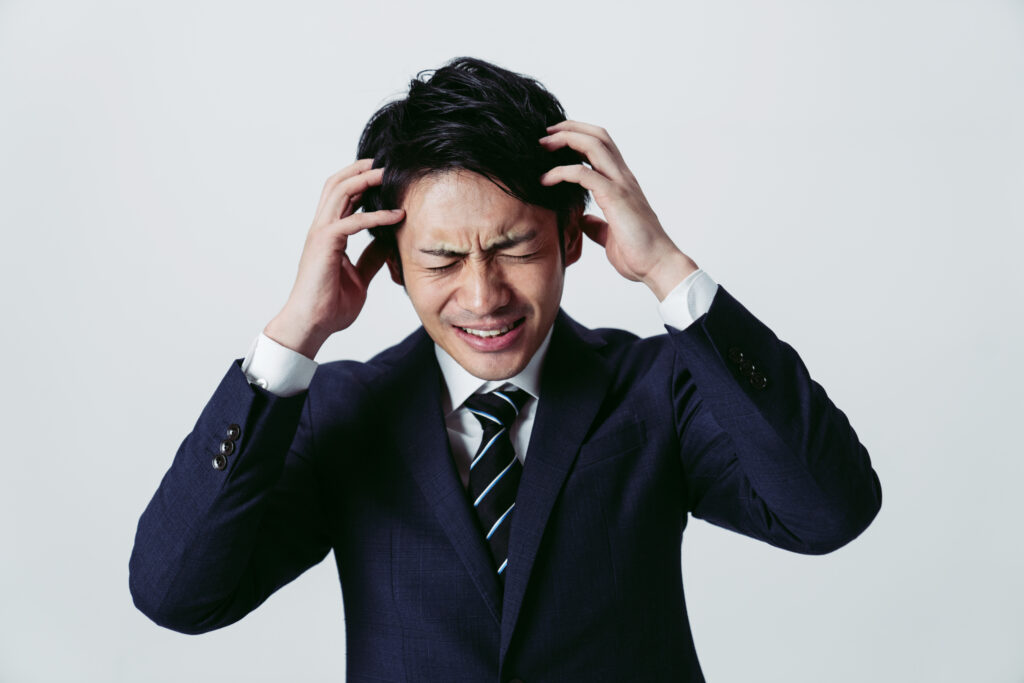
タスク管理だけに集中し過ぎると、「プライベートが疎かになる」など、ワークライフバランスが保てないケースが発生します。タスク管理を厳格に運用してしまい、絶えずタスクに追われる状態になってしまうとストレスもたまります。
この問題を解決するには、プライベートのタスクをGTDタスク管理のなかに入れておくのがおすすめです。自分にあったセルフマネジメントの方法についても、よく考えておくといいでしょう。
タスク管理は重要ですが、ワークライフバランスを保つことも重要です。仕事の効率を上げることと同じくらいプライベートな時間も大切にし、自己ケアに十分な時間を割けるよう、時間とリソースの配分を心がけましょう。
5. GTDタスク管理に適したツールやアプリ
GTDタスク管理法を最大限に活用するためには、適切なツールやアプリケーションの導入が不可欠です。
Microsoft Office(Excel)のスプレッドシートやTrelloなど、各ツールの特徴や活用方法についても詳しくご紹介します。
Microsoftoffice(Excel)で管理する
GTDタスク管理では、汎用のMicrosoft Office(Excel)を活用するのがおすすめです。Excelがない場合は、Googleのスプレッドシートでも代用できます。
また、Excelのテンプレートを使えば、特定のプロジェクトの要件に合わせたタスク管理も可能です。また、Office 365などのクラウドサービスを活用すれば、外出先からモバイルで入力するなど、リアルタイムでタスクを管理できるようになります。

Trello
Trelloには、プロジェクトやタスク管理に最適なボード管理機能があります。各ボード内で「リスト」を作成し、それぞれのリストに「カード」を追加すれば、タスクを分類し整理できます。これにより、タスクの流れや進捗状況が一目でわかります。
また、Trelloには次のような機能もあります。
- タスクの詳細設定……各カードには期限、担当者、チェックリスト、コメントなど、タスクの詳細情報が追加できる
- ドラッグ&ドロップ機能……タスクの進捗に応じて、カードを簡単にドラッグ&ドロップできる機能。優先順位に応じたタスクの変更が容易
- コミュニケーション機能……リアルタイムでチームメンバーとコミュニケーションがとれる。共有ボード上でタスクの割り当てや更新もおこなえるため、全体進捗の透明性も保たれる
Trelloは、個人のタスク管理からチームでのプロジェクト管理まで、幅広い用途で活用できるツールといえます。
参考:Trello公式サイト
Notion
Notionは、柔軟なカスタマイズオプションと、強力なデータベース機能を兼ね備えたツールです。
Notionの多機能性は、GTDタスク管理において特に効果的です。
Notionのこれらの機能をフル活用すれば、GTDタスク管理をより効果的かつ柔軟に実行できるようになります。
参考:Notion公式サイト
Asana
Asanaは、プロジェクトとタスクを視覚的に管理できるツールです。
Asanaなら、プロジェクトの要件に合わせてビューを変更できるため、自組織にあったタスク管理が簡単にできるようになります。タスクの割り振りも簡単で、個々のタスクに担当者と期限を割り当てることができ、期限内のタスク管理も容易です。
また、Asanaの進捗報告機能を使用すれば、チームでタスクの進捗状況を可視化できるようになり、必要なサポートも受けやすくなるでしょう。Asanaは、チームのニーズに合わせたカスタマイズも可能です。
参考:asana公式サイト
Todoist
Todoistは、タスク管理に特化したアプリです。
TodoistのアプリはUIにも優れており、アプリ上でタスクの追加と整理が簡単にできるのが特徴です。また、リマインダー機能を活用すれば、重要なタスクや締め切りの見逃しも防げます。
Todoistでは、ラベルやフィルターを用いてタスクをカテゴライズできるため、優先度やカテゴリ別にタスクを整理し、必要な時にすぐにタスクを見つけることができます。
参考:Todoist公式サイト
6. GTD以外に使えるタスク管理の方法
GTDタスク管理法以外にも、効率的なタスク管理の方法はいくつかあります。カンバン方式、ポモドーロ法、マインドマップなど、GTDタスク管理と一緒に利用できるフレームワークもご紹介します。
カンバン方式によるタスクやプロジェクト管理

カンバン方式は、タスクやプロジェクトの進捗状況をカンバンボード上で管理する手法です。大きなホワイトボード上で、
- 「やるべきこと(To Do)」
- 「進行中(In Progress)」
- 「完了(Done)」
などを書いていき、タスク管理を可視化していきます。
カンバン方式は、アナログ管理の要素が強い管理手法です。プロジェクトの変更や新しい優先事項が出てきたときには柔軟に対応できるため、状況の変化が激しいプロジェクト管理などに適している方法といえます。
ポモドーロ法による時間管理

ポモドーロ法とは、短い集中作業と休憩を交互におこなうことで、生産性を高める管理手法のことです。
ポモドーロ法では、25分間の集中作業(ポモドーロ)と5分間の休憩を交互におこないます。
人間の集中力は長くは続きません。短い時間で集中してタスクを処理できるようになると、休憩を頻繁に取ったとしても、結果的に組織の生産性は向上します。ポモドーロ法は、長期的なプロジェクト管理や、日々のタスクを効率よくこなすのに最適な方法といえます。
マインドマップを使った計画立案と進捗管理

マインドマップはアイデアを整理するフレームワークのひとつですが、タスク管理にも活用可能です。
マインドマップでタスク管理をする場合は、中心に重要なタスクを書き、そこから関連するタスクを枝分かれさせていき、全体を一目で把握できるようにしていきます。
マインドマップにタスクの進捗状況を記録しておけば、全体感を把握しながら、効率的なタスク管理も可能になるでしょう。
参考ツール:マインドマップ作成ツールMindMeister
7. まとめ
GTDタスク管理法は、個人の生産性と効率を向上させる強力な管理手法のひとつです。
ただし、GTDタスク管理では、タスクの収集やレビューなど、事前準備や進捗管理が重要なポイントとなります。
厳格に運用しすぎるとストレスがかかり、かえってタスク処理が遅れる場合もあります。
ITツールやフレームワークなどを併用しながら、柔軟に対応するといいでしょう。
弊社のチームマネジメントツールについて
- チームメンバーの心身状態が見えていますか?
- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?
こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。
チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!
Starteamは
- チームやメンバーの状態の可視化
- 状態に応じた改善アクションの提供
- 改善サイクルの自走化
ができるサービスとなっております。
目標達成に向けたメンバーマネジメントにより
- 離職率が約30%→約15%への改善
- 残業時間が約1/3への改善
につながった実績が出ている企業様もございます。
ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。
執筆者:嶋よしかず