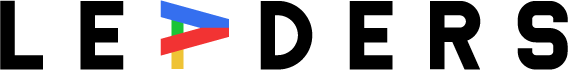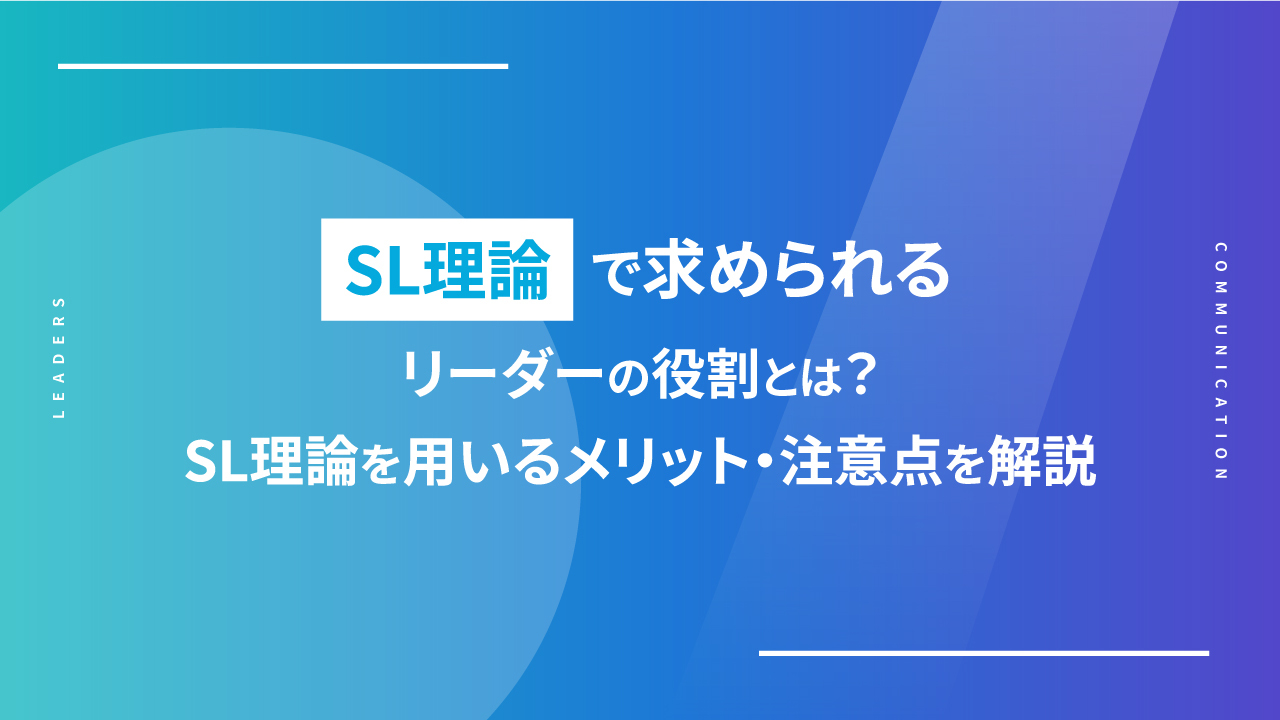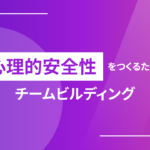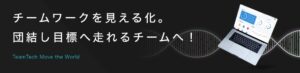組織には様々な人間がおり、それぞれが多様な経歴を持って仕事に取り組んでいると思います。
マネージャーはそのような中で、状況が違う社員たちに対し、適切なマネジメントをしていかなければなりません。
しかし、経歴も経験も異なるメンバーたち全員に対し適用できる絶対的な方法は存在しません。
つまり、メンバーの状況に応じてリーダーシップスタイルを変化させていく必要があります。
そのような場合、
「どのように部下の状況を判断したらよいのかわからない」
「リーダーシップスタイルって何?」
これらのような疑問を抱いているのではないでしょうか?
そんな時には部下の状況を4段階に分け、その段階に応じて異なるマネジメントを行う「SL理論」を活用してみましょう。
本記事ではSL理論の説明から活用方法、注意点までわかりやすく解説していきます。

1. SL理論とは
SL理論の概要
SL理論というのは「Situational Leadership」の略であり、つまり「状況に対応したリーダーシップ」のことです。
1964年にF・フィドラーが提唱した「リーダーシップスタイルはおかれている組織などの状況によって異なる」という考え方をもとに、メンバーの状況を分類し、それぞれの状況に合わせて4つのリーダーシップスタイルを使い分け、対応していくというものです。
リーダーによっては、自分の慣れているリーダーシップスタイルのみを使用しており、部下たちの成長段階に合わせたマネジメントが行われていない可能性があります。そのような組織においてこのSL理論は有効であるとされています。
状況に応じてリーダーシップスタイルを変化させていくことで、部下たちのさらなる成長を促すことができます。
SL理論におけるメンバーの4つの状況
SL理論ではメンバーの状況を4段階の「成熟度」に分類しています。
成熟度1(初心者)
新人やその業務の未経験者を指します。
新人・未経験者とはその業務においての経験がない、もしくは著しく少ないため、業務の流れ、手順等が理解できていない状態を指します。
ミスをすることを恐れて行動できていないがタスクをこなすことでチームに貢献したいという意欲が高い従業員もここに該当します。
成熟度2(中級者)
ある程度1人で業務を行える従業員を指します。
この場合、新人・未経験者に比べて業務のある程度の流れを理解できています。しかし、何をすべきかどうかを自分で判断できない状態です。
学ぶ姿勢はあるが行動に移せていない従業員はここに該当します。
成熟度3(中上級者)
業務に精通しており、最低限の指示で業務を行うことのできる従業員を指します。
高い能力を持っており、指示通りに業務を遂行することができるが、リーダーの指示がない状態ですべてをこなせるかにおいて不安が残っている状態です。
能力はあるが1人で行動できない従業員がここに該当します。
成熟度4(上級者)
高い成果をその業務にて出せる専門家として信頼できる状態を指します。
何をすべきかを完全に理解できており、リーダーからの指示がない状態においても問題なく業務が遂行でき、その責任を負うことのできる状態です。
やるべきことを理解した上で、意欲的に行動できる従業員はここに該当します。
2. SL理論におけるリーダーの役割
指示的行動と援助的行動
SL理論において、大きく分けると2つの行動指針があります。
それは「指示的行動」と「援助的行動」です。
指示的行動
指示的行動とは指示・命令・監督・統制・確認・コントロールを指します。
仕事の仕組みを作り、業務の手順などを部下に詳しく指示するなどの行動全般が当てはまります。

援助的行動
援助的行動とは部下への質問・傾聴・支援・援助・賞賛・激励を指します。
リーダーがメンバーとのコミュニケーションの円滑化と関係性の構築を目的として行う行動全般が当てはまります。
これら2つの行動指針が非常に重要です
SL理論をわかりやすく端的に言えば、これら2つの行動指針を組み合わせて4段階の成熟度別にメンバーへのアプローチ方法を変化させていくことです。
部下の変化を把握し続ける
SL理論を活用するためには、自分の部下が今、成熟度のどの段階であるのかを常に把握し続ける必要があります。
なぜなら、SL理論はこの成熟度を基準としてリーダーシップスタイルを変化させることで効果が出る方法であるためです。
部下の成熟度や状況を正確に把握・評価することは、リーダーが適切なアプローチを選択し、部下を効果的に導くための基本です。
最初は成熟度が1だとしても業務を遂行していくうちに成熟度が1から2、2から3と成長していきます。
時には段階通りではなく1から3にいきなり向上する場合もあります。その状況にリーダーは対応できなければなりません。
そのため、定期的に部下の状況を観察し、彼らの成長段階やニーズを理解することが部下のモチベーションを保つために重要なリーダーの役割の一つなのです。

部下との関係性と成果の両方に注目する
SL理論に基づくリーダーシップでは、エンゲージメントと成果の両方に注目することが重要です。部下の評価において、単に成果のみを評価するのではなく、プロセスやエンゲージメントにも焦点を当てるべきです。
部下と良好な関係性を築いていくことは必要不可欠です。しかし、それのみに注力しすぎて成果が出せない状態になってしまっては本末転倒です。
また、反対に成果のみに注力しても、SL理論を活用するために必要な部下の状況を正しく判断することができず結局は失敗に終わってしまいます。
成果を出すために良好な関係性を築き、良好かつ適切な関係性が築けているかを判断するために成果を確認する。つまり両方を同等に重視する必要があります。
また、よくSL理論に似ているとされるPM理論は、 Performance(目標達成能力)とMaintenance(集団維持能力)の2軸でリーダーシップを分類する考えです。2軸とも優れているリーダーシップになるために必要な具体的な方法に興味がある方は、是非こちらの記事もご覧ください。
【PM理論】診断テストとPM理論の概要を分かりやすく解説!あなたはどのリーダータイプ?
企業文化の形成
企業文化は、SL理論におけるリーダーシップに重要な役割を果たします。成功している組織は、製品やサービスだけでなく、従業員に競争上の優位性があると理解しています。
したがって、リーダーは部下が自身の価値を感じ、協力的で満足度の高い職場環境を作り出す必要があります。
そのためには、リーダーは部下と信頼関係を築き、成長を促進し、ポジティブで心理的安全性の高い組織文化を育む役割を果たすことが望ましいでしょう。
具体的には、情報の透明性、フィードバック受け入れの姿勢、新しいアイデアへの開かれた態度を通じて、部下が組織文化に満足感を持ち、モチベーションを高められるよう努力しましょう。
目標設定
状況に合わせて柔軟にリーダーシップを取るSL理論ですが、指針や目標が無ければ部下は方向性を失い、モチベーションも低下してしまう可能性があります。
リーダーは部下と協力して具体的な目標を設定し、それを達成するためのプロセスを管理することが、重要な役割の一つです。
目標設定を実践するために、以下にいくつかの方法をご紹介します。
共有目標
リーダーは部下と協力して目標を共有し合意を形成します。例えば、プロジェクトの完了日を設定し、それに向けてのスケジュールを作成することが目標設定の一例です。この共有された目標に向かって、部下は共通の目的に向かって協力します。
SMART目標
SMART目標(Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound)は、具体的で測定可能、達成可能、関連性のある、期限が設定された目標です。
リーダーは部下に対して、SMART目標を設定し、進捗を定期的に追跡し評価します。例えば、月末までに新商品の販売を10%増加させる目標を設定することが考えられます。
それぞれの詳細に興味がある方は、以下の記事もご参考ください。
チーム目標の設定方法|目的や方法を明確にするために必要なステップとは
3. SL理論を用いるメリット
個人の能力開発・ニーズへの対応
SL理論を活用することで、リーダーは部下の個別のニーズや状況に適応し、各個人に合わせた柔軟な対応を取る事ができます。
社員が人間である以上、状況や能力、求めるキャリアパスなどが異なるため、全社員に対して統一的なアプローチでは社員の能力を効果的に育成したり、チームの成果につなげたりすることができません。SL理論に基づくリーダーシップは、個々の部下に合わせたサポートを提供することができます。
例えば、新しいタスクに不安を感じる社員に対しては、リーダーは明確な指示や手順を提示するなどの方法を取る事で、具体的なタスクやステップを示し、社員のスキルの向上を支援することができます。
定着率の向上
SL理論を活用することによるメリットのもう一つは、定着率の向上です。
リーダーが適切な指示やサポートを提供することで、社員は「リーダーは自分のことをきちんと考えてくれているんだ」と自身の役割や業務の意義を理解し、仕事に満足感を感じやすくなります。若手社員たちが長期間働くモチベーションを維持できます。

例えば、新入社員として採用された社員が最初は業務に対する理解が不足しているためにモチベーションが低下していたとしましょう。そこで、リーダーは新入社員を放置するのではなく、迅速に新入社員の状況に気づき、適切な業務の目的説明を行うことで、新入社員は仕事の目的を理解し、会社での貢献意欲を高めることができます。
これにより新入社員と同じチームのメンバーのモチベーションも高く維持する効果が期待でき、メンバー全体の定着力が向上します。
生産性の向上
SL理論を活用することで、生産性の向上も期待できます。
リーダーがメンバーそれぞれの状況に応じて判断をするリーダーシップを取ることで、メンバーは自分たちが「ただの会社の歯車」ではなく、チームの中で重要なことの一部であると感じることができます。これにより、メンバーは自分の仕事に一層打ち込むようになり、リーダーをより信頼するという良い循環を生み出すことができます。
最終的にメンバーは職場へのエンゲージメントが高まり、結果として生産性が向上します。
加えて、上司からの適切なサポートとフィードバックがあれば、従業員は常に目標を思い起こすようになります。従業員が自分の進むべき道から外れたとき、リーダーはそこにいて、設定された目標に向かうよう補助するため、メンバーが常に同じ方向を向いている状態になります。
チームワークの向上
SL理論は、チームメンバーが協力する能力を向上させます。リーダーは、チームの成熟度に合わせてリーダーシップスタイルを選択し、チームが共同で作業する機会を提供します。
これにより、メンバーそれぞれの強み弱みなどが相互に補完し合うことで、チームの協力関係が改善し、効果的なチーム作業が可能となります。

また、SL理論によって目標をチームに伝え、自分たちの仕事や目標が全体像とどのようにつながっているのかを説明することで、その結果どうなるべきか、メンバー一人ひとりの期待値を設定することができます。
これにより長期的にチームの目標と個人の期待値がずれずに同じ方向性を向いて仕事に取り組むことができます。
4. SL理論を用いる際の注意点
ここまで、SL理論についてわかりやすく解説してきました。
しかし、この理論を活用するためには注意しなければならない点がいくつかあります。
不公平感を生む場合がある
SL理論は部下の段階に応じてリーダーシップスタイルを変化させていくものです。
そのため、成熟度によって接する時間が異なってくることがあるため、そこに不公平感が生まれてしまう場合があります。成熟度の低い従業員に対して多くの時間とエネルギーを費やす必要があるためです。この不公平感がリーダーと部下の信頼関係に悪影響を及ぼすことがあります。
例えば、新入社員のように成熟度が低い従業員に対しては、「教える、正す」行動が必要となるため、ベテランの従業員に比べ、かける時間が長くなってしまいます。
こういった、不公平感はリーダーに対する不信感にもつながってしまいますので、それを生まないためにも部下に個人によってリーダーシップスタイルを変えている旨とその理由を説明することが大切です。成熟度の低い部下に時間をかける必要性を理解させることで、不公平感を和らげることができます。
また、不公平感を回避するために、リーダーは成熟度の低い部下に十分な時間を割く必要があります。 接する時間の短さは定期的に1on1面談等を行い、その時間の密度を濃くしましょう。
1on1面談によって、個別のフィードバックと支援を提供し、部下に対する信頼を構築する機会を提供できます。信頼ゆえに任せているということがきちんと伝えられれば、時間の長さは信頼に影響しません。

的確なキャパシティの把握が必要
SL理論を活用する際に、リーダーは部下のフォローを行いながら自分の業務を行う必要があります。さらに、状況を常に把握している必要があるためそれらの業務だけでかなり工数が増えることになるでしょう。
最初からSL理論のすべてを活用しようとすると業務が回らなくなる場合があるので、リーダー経験が少ない場合は初めに従業員の成熟度だけを判断することに注力していくなど部分的に取り入れていくことをお勧めします。そういったことに慣れてきたら次はリーダーシップスタイルを柔軟に変化させていってみましょう。
リーダーシップを変化させる際、リーダーは自身のキャパシティを的確に把握することと同時に、部下とのオープンなコミュニケーションが重要になります。
部下のフィードバックを受け入れ、状況に合わせてリーダーシップスタイルを調整することで、適切なバランスを見極めるのに役立ちます。そのためにも、普段から部下との信頼関係やチームの心理的安全性を保つような職場環境づくりに力を入れましょう。
十分なコミュニケーション
SL理論を適用する際、適切なフィードバックとコミュニケーションが不可欠です。リーダーは部下とのオープンで率直な対話を通じて、各従業員の成熟度やニーズを理解し、適切な指導を提供する必要があります。
例えば、成熟度が低い新人社員がフィードバックを必要とする場合、リーダーは具体的なフィードバックを提供し、継続的な支援を提供することが望ましいでしょう。
一方で、成熟度が高い経験豊富な社員に対しては、具体的な指示を出すようなコミュニケーションよりも、目標設定や成果に関する対話が効果的です。
コミュニケーションのポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 定期的な1on1面談を実施し、部下の成長状況やニーズを共有し合う。
- フィードバックを具体的かつ建設的に提供し、改善の機会を提供する。
- 部下が気軽に質問や疑念を解消できる心理的安全性の高い環境を整える。
心理的安全性や、その高め方について詳しく知りたい方はぜひこちらの記事もご覧ください。
柔軟性を保つ
SL理論の適用は、リーダーシップスタイルの柔軟な調整を必要とします。一貫性のあるアプローチではなく、部下の成熟度やタスクに合わせてスタイルを変えることが求められます。
しかし、自身のキャパシティを鑑みながら、部下である社員の状況に合わせてリーダーシップを変えることは簡単なことではありません。リーダーはリーダーシップや対応を変える際の基準を自分なりに持つとやりやすいでしょう。
例えば、自身の業務の状況に合わせて以下のようなスタイルを取る事ができます。
- 部下の成熟度とタスク要件に合わせてリーダーシップスタイルを選択する。
- リーダーシップスタイルの変更を円滑に行うために、自己評価とフィードバックを活用する。
- チームメンバーがどのスタイルに適しているかを理解するために、常に状況を監視する。
全体の調和にも留意する

SL理論を活用すると、リーダーはチーム内で異なるスタイルを適用することになります。
この際、どうしても個人に対するサポートにい式が偏りやすいですが、チーム全体が協力し、調和するためには、リーダーの調整能力が求められます。
特にチーム内で成熟度の異なるメンバーが協力する場合、リーダーはチーム全体のバランスを考慮した上でリーダーシップスタイルを調整し、各メンバーが貢献できる環境を促進することが理想です。
6. まとめ
いかがでしたでしょうか。
最後に、SL理論について以下にまとめてみました。
SL理論とは、「状況に対応したリーダーシップ」を指します。
SL理論におけるリーダーの役割は大きく以下の5つがあります。
- 指示的行動と援助的行動
- 部下の変化を把握し続ける
- 部下との関係性と成果の両方に注目する
- 企業文化の形成
- 目標設定
注意点として、以下の点に気を付けてみましょう。
- 不公平感を生まないようにする
- キャパシティの把握
- 十分なコミュニケーション
- 柔軟性の維持
- 全体の調和に留意
弊社のチームマネジメントツールについて
- チームメンバーの心身状態が見えていますか?
- 目標達成に向けたメンバーマネジメントができていますか?
こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。
チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!
Starteamは
- チームやメンバーの状態の可視化
- 状態に応じた改善アクションの提供
- 改善サイクルの自走化
ができるサービスとなっております。
目標達成に向けたメンバーマネジメントにより
- 離職率が約30%→約15%への改善
- 残業時間が約1/3への改善
につながった実績が出ている企業様もございます。
ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。