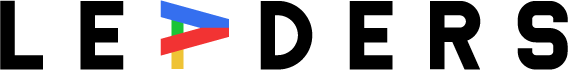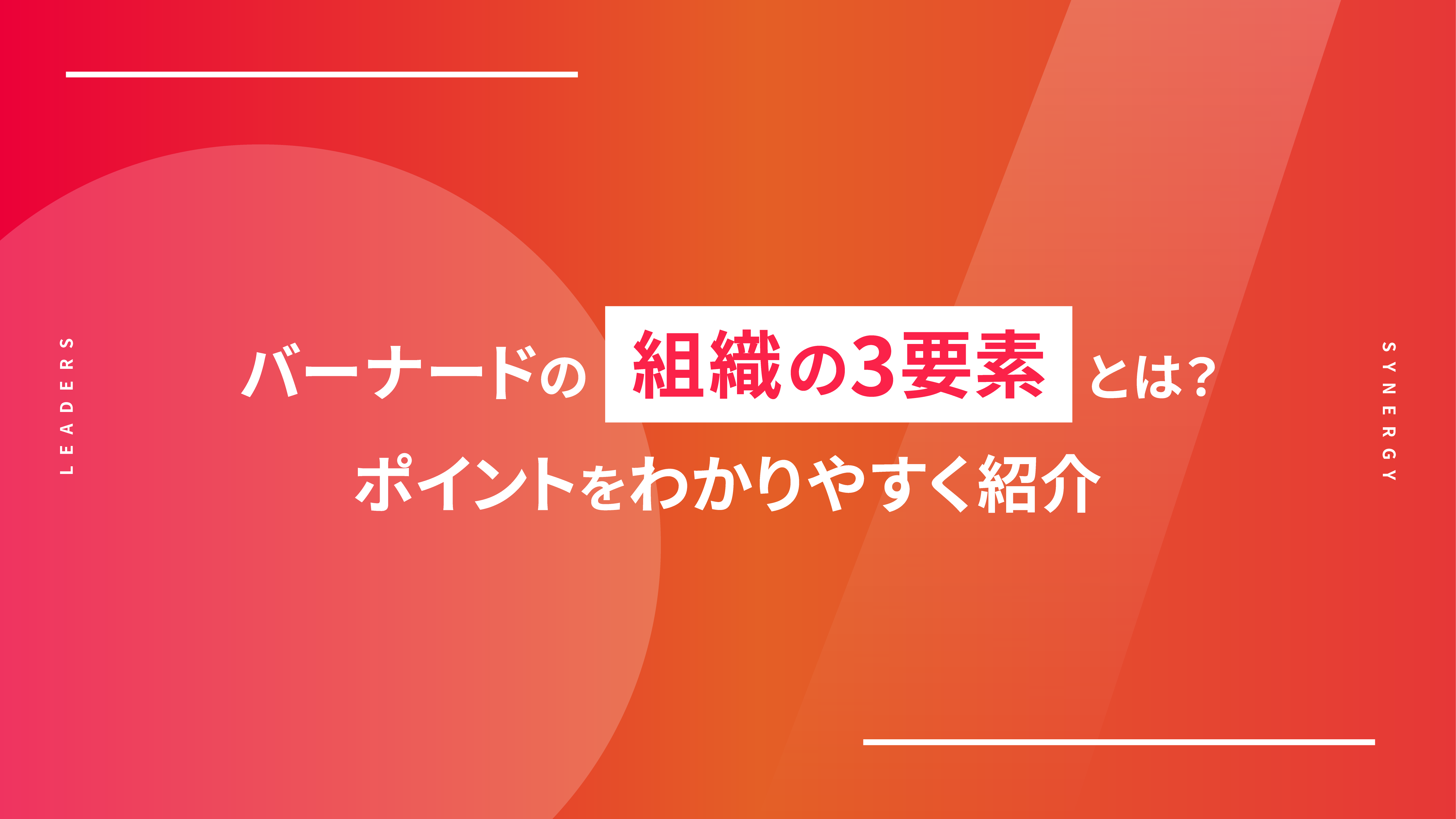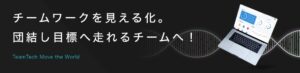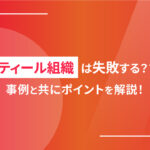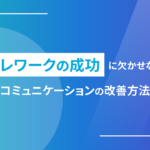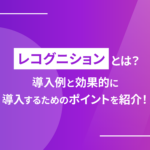組織が機能するためには、欠けてはならない3つの要素が存在します。
それはアメリカ人経済学者でもあり、自身も経営者であったチェスター・バーナード(Chester Irving Barnard)が提唱した「組織の3要素」です。
それらを正しく理解し、再度意識することによって組織を機能・存続させていくことができます。
本記事では「組織の3要素とは」という疑問から、それらをどのように強化していくかなど、日常生活などの例を用いながら幅広く解説していきます。
1. 組織の3要素とは
バーナードの提唱した組織の3要素とは、「共通目的」、「コミュニケーション」、「貢献意欲」の3つです。
バーナードはそれらを以下のように定義しています。
共通目的
1つ目の「共通目的」とは組織全体が同じ目的をもって何かに取り組むことを指します。
企業における共通目的とは「経営ビジョン」や「企業理念」などが挙げられます。 共通目的の欠落というのは時に企業においても見ることができます。
大きな企業のように1つの大きな仕事を役割分担して行っている場合、末端の社員に仕事を行う意義が伝わらず、目の前の仕事をただこなしているという状況をもたらします。
その結果、一体感や組織の一員であるという自覚が育たず、組織全体のレベルが低下してしまいます。
不測の事態や移り変わる状況への対応などの初動が遅れ、キャッチアップすることが困難になってしまったり、組織全体が保守的になり停滞してしまうこともあります。
停滞した組織の中で、本来の共通目的を忘れ、個人が自分のためだけの目的を持ち、集まったものはもはや組織とは呼べません。
そもそもバーナードは組織と集団の違いとは「共通の目的を持ったうえで集まっているかどうか」であると提唱しています。 つまり、組織が組織として存在している理由が「共通目的」を持っているということなのです。

コミュニケーション
2つ目は「コミュニケーション」です。
組織が機能するためには情報共有が不可欠です。
コミュニケーションをとることで情報共有を行い、物事を進めていきます。コミュニケーションがうまく取れなければ、組織の運営自体が大変非効率になります。それでは、いくら共通目的を持っていたとしても何も達成できません。
現代社会は情報や状況の変化が激しいです。
何かしらの分野において影響力のある組織というのはそういった変化に対応するため、常に情報共有を行っています。
また、個人レベルでも、職場の上司や部下とのコミュニケーションをとれなければその組織に残りたい、共に働きたいという気持ちが薄れてしまいます。
コミュニケーションが円滑でない場合、情報共有が行われず組織自体がそのフィールドにおいて、ついていけず、停滞してしまいます。
そして、情報だけでなく大切な人材の流失にもつながってしまう可能性があるのです。 つまり、組織が機能存続していくためにはコミュニケーションが不可欠であるといえます。
貢献意欲(協同意欲)
3つ目の「貢献意欲」とはメンバーが組織に対して貢献したいと思う意欲のことです。
自分のチームや同僚などと働きたいというモチベーションも該当するため、「協同意欲」とも言われることもあります。
組織を強固にし、高い成果を上げるために、この要素が重要な役割を果たします。
繰り返しになりますが、組織とは「共通目的」を持った個人の集まりです。
あくまでも個人なのです。
個人の努力と組織の目標が同じ方向を向いているからこそ、大きな目標を達成できる力となります。
つまり、個人が努力し貢献しやすい環境を用意することが重要になってくるというわけです。
たかが一人、されど一人です。
一人ひとりの貢献意欲を高めていくことで組織はより高みへと登っていくことができます。 組織の一人ひとりが組織に貢献したいと思う状態を保つことも組織を強固にすることには欠かせないことなのです。

2. 組織存続に必要な2条件
組織が機能することにおいて、バーナードは先ほど説明した3要素を提唱しています。
バーナードはこれら3要素に加え、組織が存続していくために必要な2つの条件も提唱しています。
それは「内部均衡」と「外部均衡」です。
内部均衡
内部均衡とは組織内部で実際の貢献度以上にメンバーにリターンがあると考えている状態です。
かみ砕いて言えば、組織がメンバーの努力や貢献をしっかり認め、それに相当するリターンを与えてくれるという認識ができているということです。
内部均衡は、先ほどの3要素、特に「貢献意欲」に通ずる部分があります。
自分の貢献度の相当するリターンが帰ってくることで、組織が自分を必要としている感覚を得ることができます。
この感覚が育つことで、帰属意識が生まれ、組織とその一員がお互いに必要とし合う状態を作り上げることができます。 それによってメンバーが組織から離脱しにくくなります。
人間関係においても、片方だけが相手を必要としている場合、その関係性は長続きしません。ある程度長続きしたとしても、それは終わりを前提とした関係性となってしまいます。
それは組織でも同じです。 内部の人から必要とされなくなってしまったら組織は存続することができません。
外部均衡
外部均衡とは、組織の立てる目標や市場にとって有益である、もしくは市場に与える価値が、組織が投資したものを上回っている状態を指します。
もちろんですが、市場において需要がないものは長続きしません。
例えば、新商品がスーパーで売り出されたとしても、それが誰も買わないものであったら、需要がないその商品はすぐにスーパーの売り場から姿を消してしまうでしょう。
売り場の担当者がどんなにその商品を押していても、需要がない、もしくは作れなければその商品は姿を消すのです。
しかし、よく売れる商品は売り場に残り続けます。なぜならスーパーに訪れる買い物客がその商品を必要としているからです。
組織も同じです。市場から必要とされていれば、その需要にこたえるために組織は存続します。
つまり、組織は組織の内部と組織の外部、両方から支えられることで存続することができます。 3要素がそろっていれば組織はある程度機能します。
しかし、長く売り場に残り続けるために、組織は内部からも外部からも必要とされる状態を作り出す必要があるのです。
弊社のチームマネジメントツールについて
組織をより強く組織改善を考えるあなたはこんな悩みを抱えていませんか?
- 組織やチームの課題を把握したい...
- チームメンバーの心身状態を把握したい...
- 目標達成に向けたメンバーマネジメントが難しい...
こんな課題を解決したく弊社はチームマネジメントツール【StarTeam】を開発しました。
チームワークを見える化し、チームリーダーのマネジメント課題解決をサポートします!
Starteamは
- チームやメンバーの状態の可視化
- 状態に応じた改善アクションの提供
- 改善サイクルの自走化
ができるサービスとなっております。
目標達成に向けたメンバーマネジメントにより
- 離職率が約30%→約15%への改善
- 残業時間が約1/3への改善
につながった実績が出ている企業様もございます。
ぜひ以下のバナーをクリックし詳細をご覧ください。
3. 組織の3要素を強化するには
これらの3要素が組織において重要であるということは理解できたと思います。
次はこの3要素を組織を運営していく中で強化していくためのポイントを紹介していきたいと思います。
共通目的を設定

共通目的には具体的なものを設定するのが好ましいです。次にとるべきアクションが明確になり、進歩状況も確認しやすくなります。
進歩状況が確認しやすくなると、「確実に前進している」という感覚を得やすくなります。
「確実に前進している」という感覚は同じ目標を持つうえで、大きな支えとなり、組織全体に一体感をもたらしてくれます。
具体例
プロジェクトにおける共通目的の設定
プロジェクトを複数のメンバーで取り掛かる際、全ての関係者が共通の目標を理解することが重要です。
例えば、新しい製品の開発プロジェクトでは、すべてのプロジェクトメンバーが「1年以内に市場に新製品を投入する」という明確なプロジェクトの目標を共有していることが不可欠です。
組織文化の共通目的
組織文化においても共通の目的が重要です。近年は組織における目的に向かって、各メンバーが裁量を持ち意思決定し実行する自律的な組織であるティール組織が注目を浴びています。
ティール組織がどのような組織なのか、気になる方はぜひこちらの記事もご覧ください。
具体的なステップ
目標の明確化

組織で共有した目的を達成するには、具体的な目標を設定する事が欠かせません。チーム全員が理解するためにも、目標は具体的で測定可能であるべきです。
目標の設定方法は様々な方法やフレームワークが存在しますが、チームやプロジェクトの目標や特性に合わせて適切に設定する事が大切です。
共有と説明
共通の目的をメンバーに共有し、その重要性と意義を説明します。この際、目標そのものを端的に説明するだけでなく、その背後にあるビジョンステートメントやミッションステートメントを活用することがでメンバーは深い理解を得ることができます。
メンバーのフィードバック
目標は一回決めて終わりではありません。適宜メンバーからのフィードバックを収集し、共通目的を調整する場合、変更を加えることで柔軟に目標を達成することができます。
注意点
注意点は以下のようなものがあります。つい当たり前だと思って見過ごしやすいですが、気を付けましょう。
柔軟性の欠如
共有目的に基づいた具体的な目標を設定したら、それにこだわりすぎず、状況に合わせて調整できる柔軟性を持つことが大切です。最初に設定した目標にこだわりすぎる場合、当初の目的からずれてしまう恐れがあります。
状況に応じて、計画を修正し、新しい情報に適応することで、共有目的に沿った目標を実現しやすくなります。
コミュニケーション不足
具体的な目的を共有した後は、なぜそれが大切なのかを仲間たちと定期的に話し合うことが重要です。形だけの目的やビジョンを掲げているだけでは、メンバーは目的に共感できず、チームに対する貢献意欲が湧きません。コミュニケーションが不足すると、メンバーは何をすべきかを理解しにくく、協力が難しくなります。
具体例を挙げて、目標に向かうプロセスを透明にするとよいでしょう。たとえば、毎週の進捗会議を通じて、進行状況や問題点を共有し合うことが効果的です。
コミュニケーションの円滑化
コミュニケーションを円滑にするには誰もがためらわず発言できる雰囲気を作り出す必要があります。 しかし、お互いをよく知らないままではなかなかためらわず発言するということができません。
それを解決するためにまずはお互いのことを理解する相互理解の場を設けましょう。
メンバー同士もそうですが、年齢や社歴、階級の異なる社員との交流の場を設けることで、ためらいなくコミュニケーションをとることができる環境づくりをしやすくなります。
具体例
リモートワークのコミュニケーション
リモートワーク環境では、出社時でのコミュニケーションよりも難しいと感じることが多くなるかもしれません。その際はビデオ会議ツールを使用して、メンバーが適切にコミュニケーションできるようにすることが理想ですが、相手の表情やチームの雰囲気が分かりにくかったり、文面でのやり取りに悩んだりすることがあるでしょう。
リモートワーク・テレワークでのコミュニケーションのポイントをわかりやすくこちらの記事で解説しています。興味のある方はぜひこちらもご覧ください。
1on1
メンバーとの距離が遠い、メンバーとより気軽に話せる関係にしたいと悩むリーダーも少なくないでしょう。そのようなときに有効なのが1on1です。1on1を行うことで、メンバーのニーズや課題を深く理解できる上に、プロジェクトの進捗状況や目標の達成度を確認し、問題解決をサポートすることができます。
定期的にスケジュールを設定し、ミーティングの終わりにアクションアイテムを設定し、次のステップを計画するとスムーズに習慣化することができるでしょう。
具体的なステップ
コミュニケーションツールの選定
適切なコミュニケーションツールを選定し、メンバーが情報を効果的に共有できるようにします。現在、社内報などを社内SNSで発信している組織も少なくありません。 組織の規模が大きくなればなるほど社員同士の面識は薄くなっていきます。そういった場合は社内SNSにて社内報を定期的に発信し、他部署や他支店の情報を発信していくことでも、コミュニケーションがとりやすくなります。
コミュニケーション施策の実施と改善
適切なコミュニケーションツールを選ぶだけでなく、そのツールを活用し、コミュニケーションを改善していくために、1on1だけでなく、以下のような施策を実施してみましょう。
- メンター制度の導入
メンター制度は、組織内での相互理解と知識共有を促進する手段です。経験豊かなメンバーが若手ビジネスマンに指導やアドバイスを提供し、双方向の学びの機会を創出します。メンター制度を通じて、メンバー間のコミュニケーションが円滑化し、スキル向上が進むでしょう。

- 社内イベントの開催
社内イベントやワークショップを通じて、メンバー同士の交流と相互理解を深めましょう。これらのイベントは、年齢や社歴、階級の異なる社員が気軽にコミュニケーションをとる場を提供します。
例えば、定期的なランチミーティング、テーマに基づくディスカッション、またはアウトドア活動など、多様なアクティビティを通じてチームメンバーが交流し、互いを理解しやすくなります。
これらの施策を実施し、実際の状況に合わせて改善を続けることで、コミュニケーションの質を向上させ、組織全体での円滑なコミュニケーション環境を築き上げることができます。
注意点
コミュニケーションのトラブルは厄介です。以下の2つの危険性に留意しましょう。
情報の不透明性
透明性は情報のオープンさや誠実さを指します。組織内では、何が起こっているのか、どのような計画が進行中なのか、重要な情報を全ての関係者に共有することが大切です。これによって、隠し事や情報の隠匿がなくなり、組織全体の信頼感が高まります。
例えば、プロジェクトの進行状況や課題について率直に共有することは、メンバー同士の信頼を築くのに役立ちます。情報を隠すことは、不信感を生み出し、コミュニケーションの円滑さに悪影響を及ぼす可能性があるので、透明性を確保することは非常に重要です。
コミュニケーションの過不足
過剰なコミュニケーションも問題ですが、コミュニケーションの不足も問題です。メンバーは疎外感を感じ、チームへの帰属意識が低くなってしまいます。定期的な会議やチームチャットを活用し、適切なバランスを意識しましょう。
貢献意欲を育てる
組織の一員にとって、自らの努力が正しく評価されていることはかなり重要なモチベーションです。 組織においてこのような評価というのは人事評価という形で可視化されがちです。
しかし、その人事評価制度が正しく貢献度を測れないものだとしたら、社員のモチベーションが下がってしまいます。

また、組織の一員だとしても、個人であることに変わりはありません。 そのことを忘れずに、個人の生活も守っていくことを忘れないようにしましょう。
チームメンバーのプライベートに必要以上に干渉せず、ライフワークバランスを考慮し仕事をアサインするなど、そういった個人を尊重する姿勢をしっかりと見せておけば、社員の中で「大切にされている」という感覚が芽生えるようになります。
そういった感覚は帰属意識につながっていき、貢献意欲になっていきます。 メンバーは組織の歯車ではなく、大切な仲間であると言葉だけでなく態度や見える形で伝えましょう。
具体例
キャリア開発プラン
メンバーに対して、スキルの向上やキャリアの成長に関する計画を提供します。例えば、トレーニングプログラムやキャリアパスの提供がこれに該当します。
賞賛や称賛
優れた成績を収めたメンバーには、賞賛や称賛を提供します。分かりやすい例だと、ボーナス、昇進、表彰状、口頭でのねぎらいの言葉などがこれに当たります。
これらのような組織やチームのメンバーが優れた業績を上げたことを認める行動をレコグニションと言います。
レコグニションの効果や行うときのポイントをこちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひこちらの記事もご覧ください。
具体的なステップ
個別のキャリア開発支援
チームのメンバーはそれぞれ異なるスキルや強みを持っており、キャリアの成長には個別の目標設定が必要です。一般的な目標だけでは、メンバーのモチベーションや努力に欠けることがあります。
メンバーに対して、彼らのスキル向上やキャリアの目標を共に考えるキャリア開発プランを提供し、メンバーを継続的にサポートすることが望ましいでしょう。これにより、メンバーは組織に還元したいと感じるでしょう。
賞賛や称賛
優れた成績を収めたメンバーを正しく評価し、その貢献を称賛しましょう。具体的な報酬や表彰の形で成果を認めることは、貢献意欲を高める強力な手段です。
ボーナス、昇進、表彰状、口頭でのねぎらいの言葉など、さまざまな方法でメンバーに感謝の意を示しましょう。これにより、メンバーは自身の努力が評価され、組織に貢献する喜びを感じるでしょう。
注意点
気を付けたいポイント2つとその対策を解説します。
不公平な報酬
成果に見合わない報酬が提供される場合、メンバーのモチベーションが低下する可能性があります。公平で透明な報酬制度を確立しましょう。
目標設定の不明確さ
メンバーに対して明確な目標を設定しないと、成果を評価する基準が不透明になり、モチベーションが低下します。個別の目標を設定し、定期的なフォローアップを行いましょう。
4. まとめ
組織の3要素はどれも当たり前なことのように思えるかもしれません。
しかし、そのどれもが組織をより強固に存続させていくには軽視してはならない要素なのです。
最後に本記事の内容を以下にまとめました。
バーナードの組織の3要素は、「共通目的」、「コミュニケーション」、「貢献意欲」で構成される。
組織の存続には、「内部均衡」と「外部均衡」という2つの条件が必要。
- 内部均衡はメンバーへのリターンと帰属感を促進し、外部均衡は市場への価値提供と需要に応えることが組織の持続性に寄与する。
組織の3要素を強化するためには、
- 測定可能で明確な共通目標の設定
- 適切なコミュニケーションツールの選定と透明性の確保
- 公平な評価制度と報酬と賞賛を含むフィードバック
が有効である。
「共通目的」を持ち、「コミュニケーション」を十分に取りながら、「貢献意欲」を育てていきましょう。